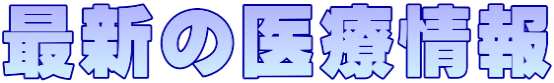
|
| 2023年8月~2024年3月 2024年(4月~8月) 2024年(9月~12月) 2025年(1月~6月) 2025年(7月~12月) |
| 2026年1月~ |
| 補聴器普及率、大きな遅れ 日本補聴器工業会は、国内の難聴者に対する補聴器普及率は2025年に約16%にとどまっていたとする調査結果を発表した。同様の調査を行う欧州なども含めた17か国中では16位と低迷しており、同会は、公的支援のあり方などに課題があると指摘している。調査は国内の補聴器メーカー10社でつくる同会などが3年ごとに実施している。約1万4000人を対象とし、国内の人口構成などに合わせて推計した。その結果、難聴者への補聴器普及率は15・6%だった。一方、17か国ではフランスとデンマークがともに55%と最も高く、英国の51%、ノルウェーの49%が続いた。日本では、難聴を自覚して医療機関を受診しているのは約4割だ。難聴を放置すると認知症になるリスクが懸念され、補聴器が必要と診断されたら速やかに使い始めることが重要だ。ただし補聴器の多くは1台10万円以上と高額で、購入費用への自治体支援にばらつきがある。同会は「医学会や関連団体と連携し、早期の聴力検査から補聴器購入まで、難聴者を支援する法制定を求めていきたい」と語った。(2026年1月30日読売新聞) 胎児の病気調べる新型出生前検査 妊婦の血液を採取して胎児の病気を調べる新型出生前検査について、慈恵医大など全国11医療機関が、胎児の全ての染色体を調べる臨床研究を2月にも始める。胎児の病気が疑われる妊婦約2000人を対象に、検査精度の検証などを行う。人間の染色体は計23 対つい 46本ある。通常は2本ずつだが、1本や3本になったり、欠失や重複があったりすると、先天性の心臓病や発育の遅れなどにつながることがある。新型出生前検査は、日本医学会の運営委員会が認証した約600医療機関で、ダウン症に関わる21番目や、18番目、13番目の三つの染色体に限り行われている。今回の研究には、慈恵医大を中心に大学病院など日本医学会の運営委が認証した医療機関が参加する。染色体の数や、欠失・重複を調べる。超音波検査などで胎児の病気が疑われたり、過去に染色体に関する病気の子どもを出産したりした妊婦で、妊娠10週以降37週未満の18歳以上を対象とする。陽性の場合には原則、診断を確定させるために妊婦の腹部に針を刺して子宮内の羊水を採取する検査を受けてもらう。研究は2030年3月末まで実施する予定。検査精度の検証に加え、この検査を行える施設の条件を整理し、検査の実施前と実施後の遺伝カウンセリングなどに必要な支援体制も整備する。胎児の病気がわかった際には人工妊娠中絶など命を巡る重い選択を迫られるケースもあるが、三つ以外の病気では検査精度が十分に確立されていない。だが、検査の認証を受けた医療機関の報告によると、美容外科や整形外科など専門外の医療機関が新型出生前検査を実施している。郵送で陽性の結果を通知し、その後の相談に応じないなどのトラブルも起きている。(2026年1月30日読売新聞)) ◆ 新型出生前検査 =妊娠9~10週以降の妊婦の血液中に混じる胎児のDNAから染色体の病気の可能性を調べる。国内では21番目(ダウン症候群)、18番目(エドワーズ症候群)、13番目(パトウ症候群)の染色体を対象に2013年4月に始まり、比較的高い精度で判定できる。 緊急避妊薬、1錠7480円 望まない妊娠を防ぐための緊急避妊薬が、2月から薬局などで買えるようになる。年齢制限はなく、保護者の同意も不要だが、販売は対面のみで、その場で薬をのむことが条件となっている。緊急避妊薬は、アフターピルとも呼ばれ、望まない妊娠を防ぐために使われる。国内では、これまで医師の処方箋が必要で、医療機関を受診しなければならなかった。海外では約90の国・地域で処方箋なしで購入でき、市販化を求める声があった。薬局などで購入できるようになるのは「ノルレボ」。2月2日から、医師の処方箋がいらない市販薬(OTC医薬品)として販売する。緊急避妊薬の市販化は国内では初めて。年齢制限なし、対面でのみ販売。希望小売価格は1錠7480円。購入に年齢制限はなく、パートナーや保護者の同意もいらない。排卵を遅らせる効果があり、性交後72時間以内にのめば8割の確率で避妊できる。(2026年1月29日朝日新聞) 病院・診療所の倒産・休廃業等が過去最多717件 帝国データバンクは、2025年の病院・医科診療所の倒産が41件、休廃業・解散が676件に上り、過去最多となる計717件が事業を続けられなくなったと発表した。件数は事業者数ベースで、施設数ではさらに多くなる。物価高騰などで病院の倒産が前年の6件から13件に倍増したほか、院長の高齢化や後継者不在によって診療所の休廃業が大幅に増えた。同社が負債1000 万円以上で法的整理となった「病院」「診療所」「歯科医院」の経営を主業とする事業者を集計した。歯科を含めた2025年の倒産件数は66件と、2年連続で過去最多を更新。内訳は、病院が13件(前年6件)、診療所が28件(同31件)、歯科医院が25件(同27件)。負債総額は242億1900万円で、3年連続で200億円を超えた。倒産の主な要因として最も多かったのは、収入の減少(48件)で、経営者の病気・死亡(5件)などが続いた。休廃業や解散が判明した医療機関も大幅に増えており、病院が15件、診療所が661件、歯科医院が147件だった。診療所と歯科医院は急増し、前年に記録した過去最多を大幅に更新した。診療所・歯科医院は、後継者がおらず閉院するケースが増えているという。同社は「病院に関しては、2026年度の診療報酬のプラス改定の影響が注目される一方、「診療所では院長が高齢化しており、休廃業は今後も増え続けるのではないか。近年は院長が急に亡くなるケースも目立ち、借金を抱えたまま閉院すると破産につながる可能性が高い」と話している。(2026年1月27日 m3.com) 「かかりつけ医」 時間外の診療や在宅医療など医療機関が地域で果たす役割を明示する「かかりつけ医機能報告制度」の運用が始まった。ほぼ全ての医療機関が3月までに都道府県に役割を届け出て、内容は順次、厚生労働省の情報サイトで公開される。厚労省は患者に医療機関の選択に役立ててもらいたいとしている。85歳以上の高齢者が増加する中で、住んでいる地域で長期療養する高齢者らを継続的に支える、かかりつけ医の存在を厚労省は重要視し、制度を設けた。制度では、大学病院など特定機能病院と歯科医療機関を除く全ての医療機関が対象となる。各医療機関は、かかりつけ医の役割について高血圧や認知症といった40疾患のうち対応できるもの、夜間や休日などの対応の有無、訪問診療や自宅での看取りの実施状況など、項目ごとに都道府県に報告する。都道府県は報告内容を確認し、厚労省のサイト「ナビイ」で公表する。サイトには現状でも医療機関ごとに診療科や診療時間が載っているが、患者は今後、より詳細な情報を入手できるようになる。また、医療機関は報告内容のうち、対応できる疾患などについては院内に掲示する。(2026年1月27日読売新聞) 培養軟骨移植で膝関節修復 患者の膝から採取した軟骨細胞を培養して移植する再生医療等製品が、変形性膝関節症を対象に新たに保険適用されたと発表した。膝の軟骨そのものを修復し、症状を改善する新たな治療法として普及が期待されるという。変形性膝関節症は軟骨がすり減り、関節の隙間がなくなることで痛みや変形が起こる疾患。進行すると歩行が難しくなる。国内の推定患者数は約1千万人で、高齢化で増加傾向にあるという。移植治療では、まず患者自身の正常な膝の軟骨細胞を採取。特殊なコラーゲンで包み細胞を約1カ月かけて増殖させた後、軟骨の欠損部に移植する。臨床試験では欠損していた軟骨が正常な軟骨と同じ組織で修復されることや、安全性を確認。培養軟骨の移植治療は、これまで2千人以上が移植を受けた。変形性膝関節症の治療は炎症や痛みを抑える薬や運動療法、人工関節に置き換える手術などがあるが、軟骨自体を治す根本治療はなかった。(2026年1月26日共同通信社) 「抗体製剤」予防接種に 厚生労働省は、感染症に効果のある抗体成分を体内に投与する「抗体製剤」を、ワクチンと同様に使えるよう予防接種法を改正する方針を示した。せき、発熱などの風邪症状や、肺炎をもたらすRSウイルス感染症の抗体製剤を新生児らへの定期接種で使えるようにすることが念頭にある。抗体製剤は、ウイルスなどの病原体に対する人工的な抗体を投与し、免疫を獲得させる。病原体の一部などを接種して体内で抗体をつくれるようにするワクチンとは仕組みが異なる。厚労省は、現行法の定義では、ワクチンではない抗体製剤を予防接種に使うのは困難だとしている。RSウイルス感染症の抗体製剤は有効性や安全性が認められており、海外では予防に使われていると説明。抗体製剤を予防接種に使う医薬品の一つとして法律で位置付け「定期接種化の議論を早期に開始することが望ましい」とした。健康被害が出た際の救済の扱いなどを部会で議論し、春ごろをめどに見解を取りまとめる。RSウイルスでは、妊婦に接種することで胎児を守るワクチンが、4月から定期接種となる予定。(2026年1月23日共同通信) 早期乳がんの重粒子線治療、5年無再発率92% 早期乳がん患者に対し、放射線治療の一種「重粒子線治療」を実施したところ、5年間再発しなかった割合が92%だったとする臨床研究結果を、量子科学技術研究開発機構QST病院のチームが発表した。乳房切除ができない患者や、切除を希望しない患者の選択肢の一つになることが期待される。早期乳がん治療では、乳房の一部、もしくは全てを切除する手術が標準治療となる。一方で、生活の質の維持や見た目の問題から、乳房を温存する治療のニーズが高まっている。QST病院では、一般的なエックス線よりも効率よくがんを死滅させられる重粒子線を使った治療の臨床研究を実施した。乳がん患者のうち、腫瘍が2センチ以下でリンパ節転移がなく、悪性度が低い60歳以上の患者12人を対象にした。1日1回照射を計4日実施し、ホルモン療法を併用して経過を観察したところ、5年全生存率は100%、5年間再発しなかったのは92%だった。1人は再発し、切除手術をした。照射後、1カ月で6人に軽微な皮膚の変化や皮膚炎があったほか、2人が肋骨骨折、3人が乳腺炎となったが回復し、安全性も確認できたという。QST病院では、対象患者を20歳以上に広げるための臨床研究や、50歳以上で照射回数を1回のみにするための臨床研究を進めている。今後、標準的な治療にするためには、多施設で同様の結果が得られるかがポイントとなる。成果は放射線治療に関する国際専門誌に掲載された。(2026年1月15日毎日新聞) 部位別のがん5年生存率 がんと診断された人が5年後に生存している割合「5年生存率」について、2016年に診断された人のデータを厚生労働省が14日、公表した。国によるがん患者情報の一元的管理が始まって初めて、部位別の5年生存率も明らかになった。15歳以上の5年生存率を主な部位別にみると、前立腺がん92.1%、乳がん88.0%、子宮頸部がん71.8%、大腸がん67.8%、胃がん64.0%、肝臓がん33.4%、膵臓がんが最も低い11.8%だった。一方、15歳未満の小児がんの種類別の5年生存率は、網膜芽腫97.6%、リンパ腫・リンパ網内系腫瘍95.7%、胚細胞性腫瘍・絨毛性腫瘍・性腺腫瘍90.2%、白血病・リンパ増殖性疾患・骨髄異形成疾患82.2%、神経芽腫・その他類縁疾患78.5%、中枢神経系・その他頭蓋内・脊髄腫瘍が60.8%などだった。(2026年1月14日朝日新聞) 認知症の4割防げる 難聴や運動不足など14のリスク要因を取り除けば、日本国内の認知症の約4割を予防したり、進行を遅らせたりできる可能性がある。そんな研究結果を、東海大の耳鼻咽喉科がまとめた。国内のデータをもとに、認知症患者へのリスク影響を推計したのは初めてという。英医学誌ランセット関連誌に掲載された。デンマークのコペンハーゲン大認知症センターは、難聴や運動不足、糖尿病、社会的孤立など14のリスク要因について、国の国民健康・栄養調査や国内の研究データなどを使って推計。その結果、リスク要因を取り除けば、国内の認知症の38.9%を予防、または進行を遅らせる可能性があることがわかった。リスク要因別の影響をみると、中年期以降の「難聴」が6.7%で最も高く、「運動不足」(6.0%)や「高LDLコレステロール」(4.5%)、老年期の「社会的孤立」(3.5%)が続いた。(2026年1月13日朝日新聞) がんを死滅させる細菌 全国の水辺でよく見かけるアマガエルから、がんの特効薬になるかもしれない天然細菌が見つかった。大腸がんを起こさせたマウスの静脈に1回注射したところ、患部に集まってがん細胞を攻撃し、腫瘍は1~2日で完全消滅。細菌も一定期間で死滅し、臓器に定着して悪影響を及ぼすことはなかったという。発見した北陸先端科学技術大学院大の研究チームは「画期的な細菌だ」として、他の種類のがんに対する効果の確認と、より安全な投与方法や既存治療との組み合わせの模索を急いでいる。がん治療の基本は、手術・抗がん剤・放射線の3本柱だ。近年は、外部から侵入する異物に対する体の見張り役である免疫の力を立て直す免疫療法が新たな選択肢として加わった。代表例が、免疫の働きを抑えるタンパク質「PD-1」の働きを抑え、免疫に本来の攻撃力を取り戻させる免疫チェックポイント阻害剤だ。ただ、免疫療法は、よく効く患者がいる一方で、効かない患者も少なくない。効果が出るまで時間がかかることや免疫関連の副作用、高額な費用負担といった壁が残る。そこで「誰に、どの治療を組み合わせれば効くのか」を見極める視点が重要化。遺伝子を改変したウイルスでがん細胞を壊して免疫を活発化させる方法や、人工多能性幹細胞(iPS細胞)由来の免疫細胞を大量に用意し素早く投与する方法など、次の手が次々に試されている。この流れの中で、少し異色な存在に見えるのが「細菌」だ。細菌を用いたがん治療は150年以上前から検討されていたが、近年、腫瘍の中の酸素が乏しい環境や免疫が働きにくい環境に、特定の細菌が住み着きやすいことが分かり、再び注目が高まってきた。(2026年1月10日産経新聞) 化学放射線と免疫治療薬の併用 京都大病院は9日、食道がん患者に対し、抗がん剤と放射線を組み合わせた標準的な治療とともに、免疫機能を後押しする「免疫チェックポイント阻害薬」を併用する治療の臨床試験(治験)を実施し、有効性と安全性を確認したと発表した。手術ができない患者への適用など、手術以外の治療の拡大が期待される。京大病院によると、食道がんの一般的な治療では、抗がん剤と切除手術を組み合わせる。体力的な理由で手術が難しい場合や、食道を残したい人には、抗がん剤と放射線を組み合わせた化学放射線療法があるが、再発率の高さが課題だった。治験は進行度が異なる患者約40人を対象に5病院で実施。4カ月間の抗がん剤投与と1カ月間の放射線治療と並行し、免疫チェックポイント阻害薬の「オプジーボ」を1年間投与した。画像検査でがんが見えなくなる「完全奏功」と判断されたのは7割。1年後の生存率は9割を超え、化学放射線療法だけよりも良好な結果となった。副作用として想定された重篤な肺炎の発生は5%で、安全性は確保されたと判断した。(2026年1月9日共同通信) がん遺伝子パネル検査 がんの遺伝子の変化を網羅的に調べて対応する治療を探す、がん遺伝子パネル検査。国内でこの検査を受けた5万人超についての分析を、国立がん研究センターなどのチームが発表した。検査に基づく治療を受けられたのは8%で、がんの種類によっても差があった。がんは遺伝子の変化によって起きることから、近年は遺伝子の変化を調べ、それに合った治療をするゲノム医療が推し進められている。100種類以上の遺伝子を同時に調べるがん遺伝子パネル検査は2019年に保険診療になった。チームは、19~24年に検査を受けた約5万4千人について分析した。検査の結果、治療法のある遺伝子の変化が見つかったのは73%にのぼったが、国内未承認薬や治験段階のものも含まれ、実際にその治療を受けられたのは8%だった。ただ、経年的に改善してきており、19~20年には6%だったが、23~24年には10%に増えていた。がんの種類によっても治療に結びつく割合には差があり、患者が多く薬剤開発が進んでいる肺がんは20%、甲状腺がんは35%と高かった。一方で、薬剤の開発が進みにくい膵がんや肝臓がんは2%に満たなかった。患者の生存期間との関係を見ていくと、科学的根拠が強く国内承認済みの薬がある遺伝子変化が見つかった人は、最も予後が良かった。有効性のある薬が国内未承認薬だった場合でも、予後が良い傾向にあった。治験などを通じて未承認薬が使えれば、患者が恩恵を受けられる可能性がある。論文は6日、医学誌「ネイチャー・メディシン」に掲載された(2025年1月8日朝日新聞) パンデミックへ備え ワクチン開発 新型コロナウイルスの感染拡大のように感染症のパンデミックはいつでも起こり得る。広島大は9月、コロナ禍で国産ワクチンの開発が遅れたことを踏まえた国の要請に基づき、速やかに治験薬を製造、供給する施設を完成させる。鉄骨4階建て延べ約2600平方メートルの施設の建設が進む。大学がワクチン製造施設を持つのは国内で初めて。2027年に稼働を始める新施設はパンデミック発生時、国の要請に応じてワクチンを開発する。成分決定後に1万人分を3カ月程度で生産。初期データで安全性と有効性を確認できれば量産できる製薬会社などに引き継ぐ。平時には新興企業や製薬会社から治験薬の製造を受託する。(2026年1月7日中国新聞) 妊婦健診の「標準額」設定へ こども家庭庁は、妊婦や胎児の状態を調べる妊婦健診について、価格が医療機関によってばらつきがあるため、目安となる標準額を設定する方針を決めた。これより高く設定している医療機関が価格を引き下げ、妊婦の経済的負担の軽減につなげる狙いがある。有識者会議に方針を示し、了承された。妊婦健診は、妊娠の週数に応じて、妊婦の血糖値や感染に関する検査、胎児の成長を確認する超音波検査などのため、14回程度行われる。価格は医療機関が自由に設定しており、自治体による助成額にもばらつきがある。こども家庭庁によると、地域別の平均負担額は関東甲信越で約1万9000円に上る一方、中国・四国では約7500円と、1万円以上の開きがある。(2026年1月7日読売新聞) 帯状疱疹ワクチンは心臓病、認知症、死亡リスクの低減 帯状疱疹ワクチンは中年や高齢者を厄介な発疹から守るだけではないようだ。新たな研究で、このワクチンは心臓病、認知症、死亡のリスクも低下させる可能性が示された。米国感染症学会年次総会で発表された。米疾病対策センター(CDC)によると、米国では3人に1人が帯状疱疹に罹患することから、現在、50歳以上の成人には帯状疱疹ワクチンの2回接種が推奨されている。帯状疱疹は、水痘の既往歴がある人に発症するが、CDCは、ワクチン接種に当たり水痘罹患歴を確認する必要はないとしている。1980年以前に生まれた米国人の99%以上は水痘・帯状疱疹ウイルスに感染しているからだ。水痘・帯状疱疹ウイルスは、数十年間にわたって人の免疫システム内に潜伏し、その後、再び活性化して帯状疱疹と呼ばれる痛みやチクチク感、痒みを伴う発疹を引き起こす。水痘への罹患経験がある人なら年齢を問わず帯状疱疹を発症する可能性があるが、通常は、ストレスにさらされ、免疫力が低下している50歳以上の人に多く発症する。米国の107の医療システムから収集した17万4,000人以上の成人の健康記録を分析し、帯状疱疹ワクチン接種者の健康アウトカムをワクチン非接種者のアウトカムと比較した。ワクチン接種者は接種後3カ月~7年間追跡された。その結果、帯状疱疹ワクチンの接種により、血流障害による認知症のリスクが50%低下、血栓のリスクが27%低下、心筋梗塞や脳卒中のリスクが25%低下、死亡リスクが21%低下した。(2026年1月5日米国感染症学会年次総会M3.com) 全自動で磨く歯ブラシ開発 早稲田大発のベンチャー企業が、口にくわえるだけで自動的に歯を磨ける「ロボット歯ブラシ」を開発した。短時間で気軽に歯を磨くだけでなく、子どもの歯磨き習慣定着や、1人での歯磨きが難しい障害者や介助者らの負担軽減などにも期待する。春にも一般販売を始める。口内の衛生環境を保つことは、歯周病などの感染症予防にもつながる。縦6センチ、横10センチ、奥行き5・5センチの本体に、複数のブラシを備えたU字形の装置を付けて使う。口にくわえて起動すると、ブラシが円を描くように振動しながら移動し、上下の歯の表裏や歯間を磨いていく仕組みだ。ブラシの動きは本体の二つのモーターで制御。ブラシの角度や制御システムを工夫し、最短1分で手磨きと同程度まで歯垢を除去できるという。先端を付け替えると頬や舌の筋肉のマッサージもできる。高齢者の誤嚥予防や、筋萎縮性側索硬化症(ALS)の患者の口を開けやすくしたり唾液量を増やしたりして、口内を清潔に保つことが期待できるという。(2025年1月5日共同通信社) ゲノム編集で筋ジストロフィー治療 筋ジストロフィー症で損傷した筋肉が回復しにくくなるのを、ゲノム編集を使って治療する方法を、京都大学と武田薬品工業の研究チームが開発した。これまでの治療法よりも効果的で持続することをマウスの実験で確かめた。今後、実用化に向けて安全性などを確かめる。研究チームが対象にしたのは、遺伝性疾患のデュシェンヌ型筋ジストロフィーで、遺伝子の異常でジストロフィンというたんぱく質ができず、筋肉の細胞が傷ついても修復しにくい。研究チームは、遺伝子を組み込むのにゲノム編集技術を使う方法を開発。その結果、細胞修復に欠かせない筋幹細胞に、遺伝子を効果的に組み込めることをマウスの実験で確認した。さらに、ジストロフィンを作り出す効果も1年以上にわたって持続した。研究チームは、ほかのタイプの筋ジストロフィーも、組み込む遺伝子を変えることで治療できる可能性がある。今後は人への臨床応用に向けて、さらに研究を進めていきたいと話した。研究成果は12月17日付の米科学誌セルリポーツに掲載された。(2026年1月5日朝日新聞) 「スギ花粉米」活用した医薬品開発 政府は、花粉症の症状を和らげる効果が期待される「スギ花粉米」を原料とした医薬品の開発を加速させる。有効性や安全性の検証のため、臨床前試験を年内にも行い、早期の実用化を目指す。「国民病」とも呼ばれる花粉症対策の切り札にしたい考えだが、医薬品の承認手続きやスギ花粉米の量産化が課題となる。スギ花粉米は遺伝子組み換え技術を使い、花粉症の原因物質の一部を含ませたものだ。少量で摂取を続け、花粉への耐性をつけることで、アレルギー反応が起きにくくなると期待される。スギ花粉症に悩む国民は約4割を占めるとされ、花粉症を含むアレルギー性鼻炎の医療費は年間4000億円に上ると推計される。政府は23年、花粉症に関する関係閣僚会議を設置し、発症、発生源、飛散の3分野で対策を進めている。(2025年1月5日読売新聞) |
|
たはら整形外科 |