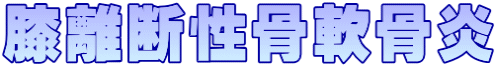 |
|
| 膝離断性骨軟骨炎は、日常生活動作やスポーツ傷害などで繰り返される慢性的な刺激で発生します。関節軟骨に血行障害が生じ軟骨下骨が壊死する疾患です。進行すると骨軟骨が離断(関節内に剥がれ落ち遊離)すると多彩な症状を訴えます。10歳代の男性に多く認められます。膝の内顆部(80〜90%程度)に好発します。時に外顆部や膝蓋‐大腿関節面にも認められます。 症状 症状は膝の痛みや脹れです。歩行や運動で悪化し安静で軽快します。時に夜間痛を認めます。進行すれば骨軟骨が遊離して膝のひっかかり感や雑音(ゴリッと音がする)、不安定感、ロッキング現象・嵌屯症状(遊離した骨軟骨が大腿骨と脛骨の間に挟まれて膝の曲げ伸ばしが困難になる状態)を認めます。なお、非荷重面(体重がかからない部位)の骨軟骨炎では症状を訴えないこともあります。また、外顆部に発生した症例は半月板損傷(特に円板状半月損傷)を合併することがよくあります。 診断 ●レントゲン検査では5つに分類されます。 第1期:レントゲンで異常がない。 第2期:骨透亮像を認める状態。 第3期:骨透亮像に加え硬化像を認める状態。 第4期:軟骨下骨の剥離を認める。 第5期:遊離体(骨片が完全に遊離)を認める状態。 ●MRIでは4つに分類されます。 第1期:軟骨が軟化している状態。 第2期:軟骨に亀裂を認めている状態。 第3期:軟骨下骨の一部の骨片が剥離している状態。 第4期:骨片が完全に遊離している状態。 ●関節鏡では4つに分類されます。 Stage1:軟骨が軟化している状態。 Stage2:軟骨に亀裂がある状態。 Stage3:骨片が部分的に剥がれた状態。 Stage4:骨片が完全に遊離した状態。 このMRIの分類や関節鏡の分類は治療の指針になります。 治療 一般的に病期分類(関節鏡やMRI)で決定されます。 1)保存的治療(手術しない方法) Stage1とStage2は保存的治療となります。スポーツを3〜6ヶ月間中止していただきます。その間、免荷歩行(体重をかけないで杖で部分歩行)を行います。ギプス包帯や膝可動域制限サポーターを検討することもあります。また、骨髄ドリリング法(病巣部に穴を開け血液と骨髄液の反応を利用して修復を促す方法)も検討されます。 2)手術的治療 Stage3とStage4は手術的治療となります。術式は整復固定術(自分の骨をネジの代わりにして固定する方法)や自家骨軟骨移植術(膝の後部は非荷重部なので骨と軟骨片を採取し病巣部に植える方法)や自家培養軟骨移植術(患者さんの軟骨を培養して貼り付ける方法)などが検討されます。
|